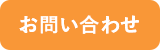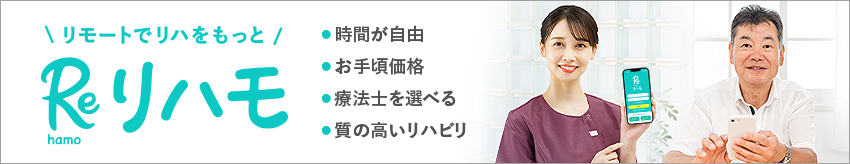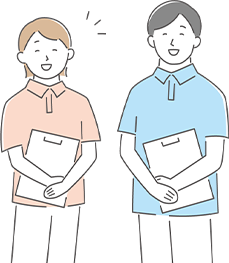更新日:2025.03.13リハビリ脳卒中発症後「6ヶ月の壁」6ヶ月以降に身体機能や歩行、ADLは改善するのか。科学的根拠をもとにリハビリの可能性を解説。【理学療法士監修】
脳卒中は多くの人々に影響を与える疾患であり、発症後のリハビリが重要な役割を果たします。
一般的に、脳卒中後6ヶ月が回復の目安とされ、この時期を過ぎると大きな改善は期待しにくいと考えられていました。
しかし、最新の研究では、6ヶ月以降も適切なリハビリを続けることで身体機能や歩行能力、日常生活動作(ADL)の向上が可能であることが示唆されています。
本記事では、その科学的根拠とリハビリの可能性について詳しく解説します。
目次
脳卒中後6ヶ月の壁とは?
6ヶ月以降の回復は本当に難しいのか?
脳卒中後の回復は急性期(発症〜数週間)、回復期(数週間〜6ヶ月)、慢性期(6ヶ月以降)に分かれます。
従来、6ヶ月以降の回復は困難とされていましたが、近年の研究では、適切な介入により慢性期にも回復が見込めることが分かっています (McIntyre et al., 2012)。
脳卒中発症後のリハビリの流れ
急性期、回復期、慢性期の特徴
-
急性期:早期離床と廃用症候群の予防が重要。
-
回復期:機能回復が最も進む時期で、積極的なリハビリが推奨される。
-
慢性期:回復速度は緩やかになるものの、適切なリハビリによりさらなる改善が可能。

歩行能力の回復について
6ヶ月以降でも歩行改善は可能?
最新の研究では、6ヶ月以降でも歩行改善は可能であることが示されています。
この研究では、発症から6ヶ月以上経過した脳卒中患者を対象に、理学療法を行った群と、プラセボまたは無介入の群を比較しました。
その結果、短距離および長距離歩行能力が改善していました(歩行速度の平均差0.05m/s、歩行距離の平均差20m)。
脳卒中後の回復における「回復の停滞(プラトー)」という概念に疑問を投げかけ、地域でのリハビリテーションを行うことで、
6ヶ月以降も改善する可能性を示しています (F. Ferrarello et al.,2024)。
日常生活動作(ADL)の回復について
6ヶ月以降も日常生活動作は改善する?
生活期の脳卒中患者においても、適切なリハビリがADLの改善に寄与することが報告されています。
特に、運動プログラムや家庭でのリハビリが機能向上に有効であることが示されています(Ferrarello et al., 2024)。
日常生活動作改善に効果的なリハビリ
日常生活動作(ADL)の改善には、実践的なリハビリを繰り返し行うことが重要です。
ただ行うだけではなく、お風呂やトイレ、階段など実際の生活の場面で、
「どの動きが難しいのか」「道具を使うと簡単・安全にできないか」「手伝ってもらうとしたらどのようにすれば楽にできるか」を考えながら改善していきます。
また、ご家族のサポートも日常生活動作の改善を後押しします(Chevalley et al., 2023)。
本人のモチベーションを維持するために、日常生活の中で積極的に動く機会を作ることや、リハビリの進捗を記録して励ますことが推奨されています。
さらに、夜廊下を歩くときのために人感センサーのライトを設置することや、手の届きやすいところに台を置くなどのちょっとした環境調整でも、本人の過ごしやすさは大きく改善します。
まとめ
脳卒中後6ヶ月を過ぎても適切なリハビリを続けることで、身体機能や歩行能力、ADLの改善が可能です。
今直面している課題や目指す目標を整理した上で、ひとつずつ向き合って練習していくことで、緩やかにではありますが歩行も日常生活動作も改善していく可能性があります。
心が折れそうになる時もあるかと思いますが、希望を捨てることなく日々過ごしていただけると幸いです。
関連記事

2025.04.14リハビリ
【2025年版】療法士は脳卒中の運動麻痺の検査「Brunnstrom stage」で何を見ているか 当事者・ご家族向けに解説

2025.04.07リハビリ
脳卒中の患者の運動と筋緊張の関係:システマティックレビューと臨床的な感覚から理学療法士が解説

2025.03.28リハビリ
その人らしさを起点としたゴール設定がリハビリでは重要?

2025.03.27リハビリ
療法士との信頼関係がリハビリの効果を高める理由 ~「人と人」として向き合うことが、からだの回復につながる~

2025.03.19リハビリ
反張膝の原因と改善へのヒント