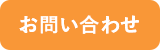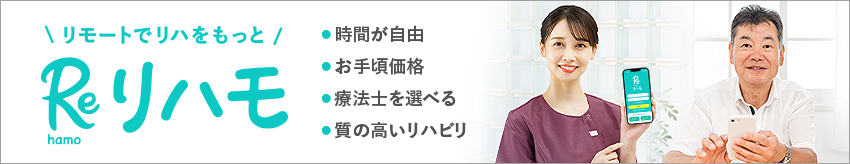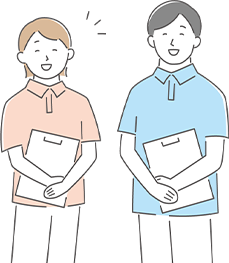更新日:2025.04.07リハビリ脳卒中の患者の運動と筋緊張の関係:システマティックレビューと臨床的な感覚から理学療法士が解説
「運動=筋緊張が上がる」は本当か?
「運動したら筋緊張が強くなるから、あまりやらない方がいいんじゃないか」
リハビリの現場やご家族との会話で、そんな声を聞くことがあります。実際、痙縮(けいしゅく)と呼ばれる筋肉のつっぱりがあると、運動が悪化要因になるのではないか…と心配されるのも無理はありません。
私自身の臨床経験から言うと、運動=筋緊張が上がるという単純な図式では語れないと感じています。
たとえばスクワットをしていると、麻痺側の肘や手首が自然と伸びてくる方も少なくありません。
運動後に足首が少し柔らかくなり装具のおさまりが良くなる方も見てきました。
一方で、「歩行中に麻痺側に体重が乗らない」「全身が緊張していて努力性が強い」といった場合には、クローヌスが長引いたり、緊張が一時的に高くなることもあります。
このように、運動=筋緊張があがるではないというのが、現場の実感です。
本記事では、システマティックレビューという、いくつもの研究結果を集めて、「全体としてどうなのか?」を客観的に調べた研究を通して、現場感と合わせて運動と筋緊張の関係について考えます。
筋力トレーニングと痙縮の関係についての研究
では、科学的にはどうなのでしょうか?
2021年に発表されたシステマティックレビュー(Blancoら,2021)では、痙縮のある神経疾患の患者(主に脳卒中)に対して、レジスタンストレーニング(筋力トレーニング)がどのような影響を与えるかを10のランダム化比較試験(RCT)をもとに検証しています。
その結果、筋トレによって痙縮が悪化することはなかったという結論が出ています。
✔ 痙縮への影響:
-
4つの研究では筋緊張(痙縮)は変わらず
-
さらに4つの研究では筋緊張が改善
-
使用された評価法の多くは「改良アシュワーススケール(MAS)」で、科学的にも信頼性のある評価
つまり、適切に運動すれば、筋緊張は悪化しないばかりか、むしろ改善する可能性があるというわけです。
✔ 筋力・機能への影響:
-
ほとんどの研究で筋力が向上
-
多くの研究で歩行やバランスなどの機能面でも改善
-
特に水中運動やスクワットなどの下肢筋力トレーニングが効果的という結果もありました
以上より、筋力トレーニングは筋力の向上と歩行やバランスなどのパフォーマンス改善に結びつき、痙性への悪影響はない可能性が示されているかと思います。
参考:del Blanco, Juan Abal, and Yaiza Taboada-Iglesias. “Effects of resistance exercise in patients with spasticity: Systematic review.” Apunts Sports Medicine 56.212 (2021): 100356.
運動を行う際の注意点
このレビュー結果と現場感覚を合わせて考えると、「どんな運動を、どう行うか」が鍵になります。
たとえば:
-
麻痺側にしっかり荷重をかけられるか?
-
全身に力が入りすぎていないか?
これらを意識することで、運動後の緊張の変化を穏やかにし、クローヌスなどの不快症状を減らすことができます。
また、運動後にストレッチボードを使って下肢全体をゆっくり伸ばすといったケアを加えると、より良い効果が期待できます。
まとめ:運動=筋緊張悪化ではない。
今回のシステマティックレビューと臨床的な観察から見えてきたのは、以下のようなポイントです:
-
筋トレや運動で痙縮が悪化するわけではない
-
むしろ運動の質や工夫次第で、筋緊張や機能が改善する可能性がある
-
一方で、負荷が強すぎたり、無理な動作は緊張を上げるリスクがある
-
トレーニング後のストレッチやクールダウンも有効
「動くと緊張が上がるのでは」と心配している方にこそ、適切な運動が安全で有効なリハビリの一歩になることを知っていただきたいです。
次回は「どういう仕組みで運動後に筋緊張が軽減するのか」についてご紹介したいと思います。