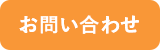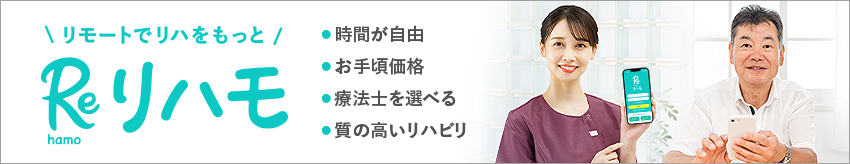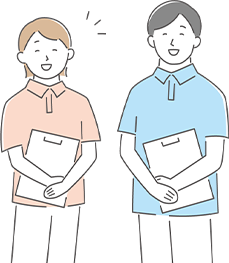更新日:2025.04.14リハビリ【2025年版】療法士は脳卒中の運動麻痺の検査「Brunnstrom stage」で何を見ているか 当事者・ご家族向けに解説
脳卒中を経験された方にとって、「リハビリ」という言葉は切っても切り離せないものだと思います。中でも、運動麻痺からの回復過程を評価する指標として知られる「Brunnstrom(ブルンストローム)ステージ」は、リハビリ専門職の間では非常にポピュラーな概念です。
今回は、このBrunnstromステージ(以下、Br.s)について、理学療法士としての実体験や患者さんとの関わりを踏まえながらご紹介していきます。
Brunnstromステージとは?
Brunnstromステージは、脳卒中による運動麻痺がどの程度回復してきているかを6段階で示した評価法です。
開発者であるスウェーデンの理学療法士、Signe Brunnstrom(シグネ・ブルンストローム)によって提唱され、運動麻痺の回復を「弛緩→反射の出現→協調的な動きの回復」へと段階的に捉えるものです。
このステージの良いところは、患者さん一人ひとりの回復過程の“今”を把握できることです。
つまり、回復の見込みや適切なリハビリのゴール設定、今、どのようなリハビリが必要かを考えるのに役立ちます。
なぜBrunnstromステージをみるのか?
例えば、こんな場面があります。
「Br.sⅢだから、長下肢装具は不要になるはず」
「発症から〇ヵ月で今のステージがこれなので、3ヶ月後にはこうなっているだろう…」
このように、ステージごとの特徴を踏まえて、どのようなリハビリをすべきか、どのようなサポートが必要かといった方針を立てることができます。
また、発症からの時間経過との兼ね合いで予後の見立てにも使われることが多いです。
ただし「Brunnstromステージだけで判断しないこと」が重要です。
筋緊張、感覚障害、注意障害など“麻痺以外”の要素も一緒に見ていくことが必要不可欠です。
各ステージの特徴(下肢編)
ここでは、下肢(脚)におけるBrunnstromステージを例に、各段階の特徴と臨床での見方を紹介します。
ステージⅠ:弛緩(しかん)
-
特徴:完全な弛緩。自分の意思でも、外からの刺激でも動かない状態。
ステージⅡ:反射の出現
-
特徴:反射的な動きや、特定の誘導で少し力が入る。刺激によって膝がピクッと動いたり、筋緊張が少しずつ出てくる段階です。
ステージⅢ:共同運動パターンの出現
-
特徴:足全体を“ひとまとまり”として動かせる。例えば膝を曲げたら股関節や足首も同時に動いてしまう。
ステージⅣ:分離運動の一部回復
-
特徴:座った状態で膝を伸ばしたり、足首を上げたりと、少しずつ「単独の動き」が可能に。
ステージⅤ:複雑な運動の実施
-
特徴:立った状態で足を後ろに上げたり、足首の動きだけを出したりできるように。
ステージⅥ:協調運動の回復
-
特徴:ほとんどすべての動きが可能。ただしスムーズさやスピードには左右差が残る。
Brunnstromステージをどう活かすか?
リハビリの現場では、Brunnstromステージを単なる“評価”ではなく、今できること・次に目指すべきことを共有する「共通言語」として使っています。
ステージが分かることで、その他の症状と合わせて歩行や日常生活でのできることのイメージを共有しています。
このように、Brunnstrom stageは本人・家族・医療者の間で、状態や方針を理解し合うためのツールとして有効です。
最後に:ステージは“回復の地図”
Brunnstromステージは、リハビリの現在地を確認する「地図」のようなものです。ただし、地図の通りに進むとは限らないのが回復の難しさでもあります。
一人ひとりの道のりに合わせて、時には立ち止まり、時には戻りながらも、今どこにいるのかを可視化することで、前に進む勇気が生まれます。
リハビリの現場で大切なのは、「今のステージを悲観することではなく、そこから何ができるかを考えること」。Brunnstromステージは、そんな前向きなリハビリを支える心強い指標です。